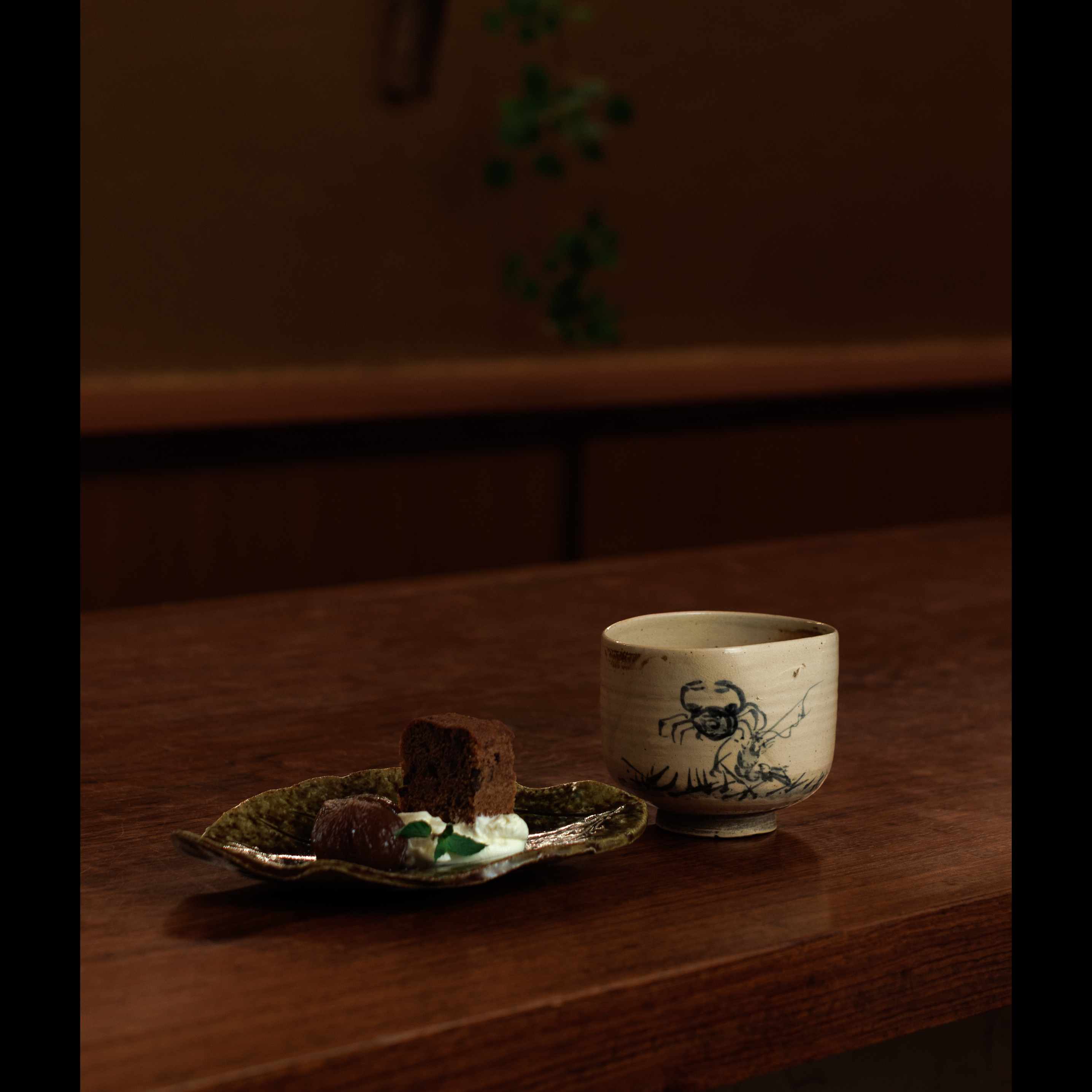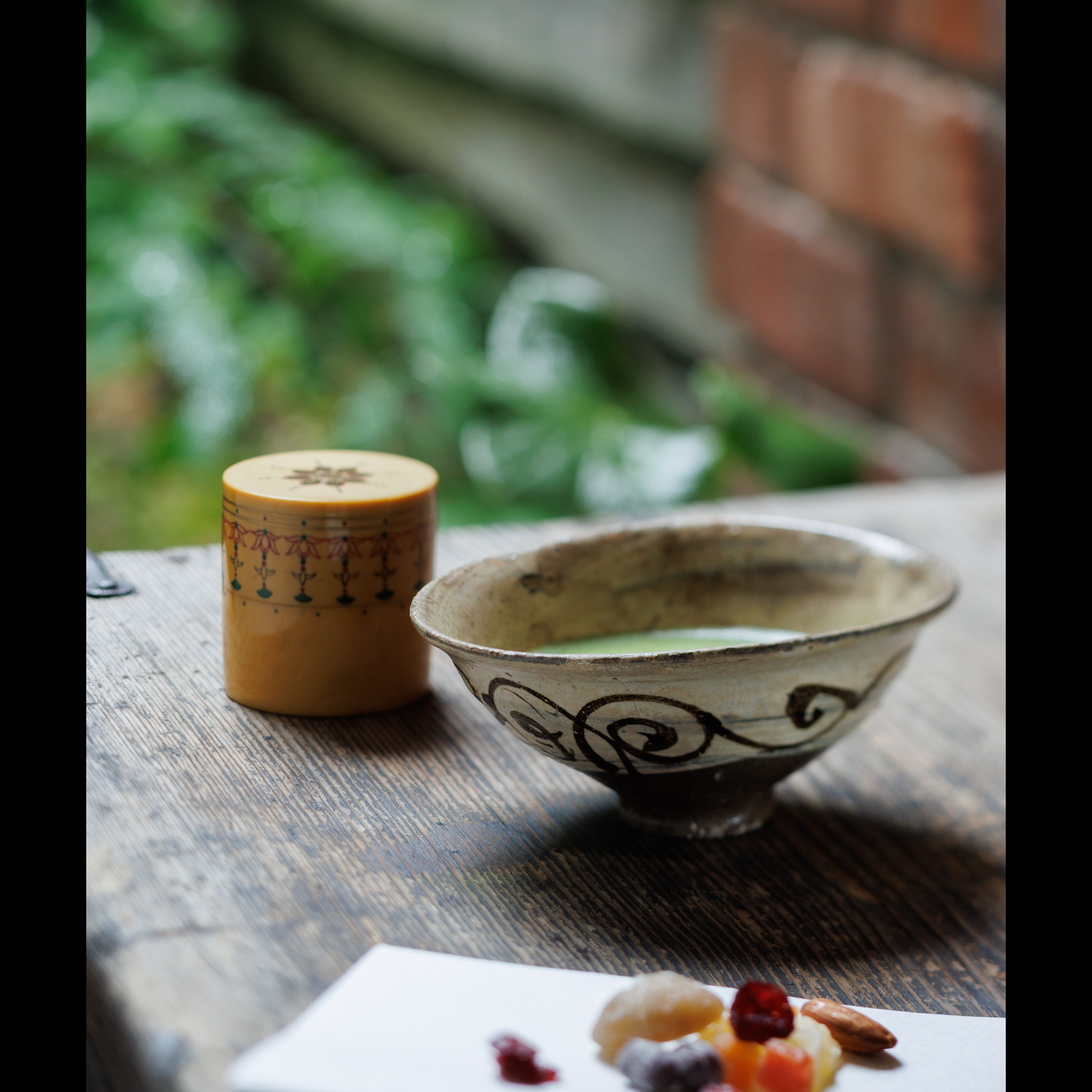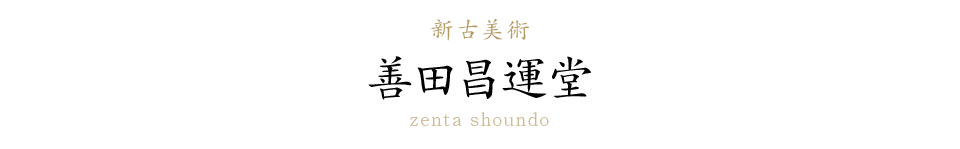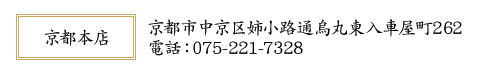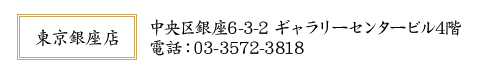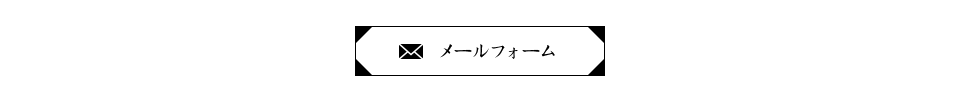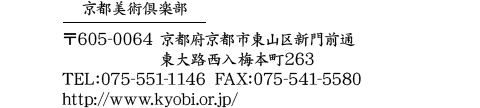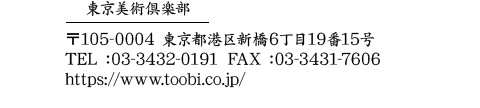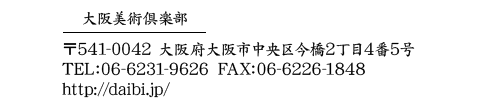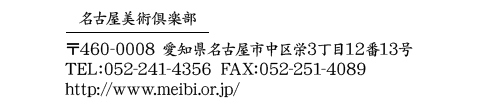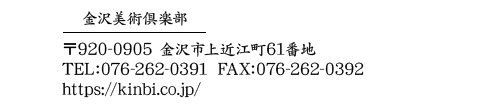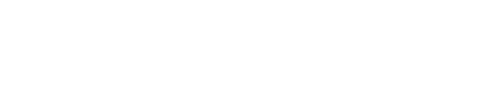絵御本海老蟹図茶碗 / 魯山人木の葉皿
絵御本海老蟹図茶碗
高:9.0 径:11.3
魯山人木葉皿 五客
高:4.3 径:22.5
企画展「日々好日 – Hibiyokihi」
茶碗と菓子器で味わう十二か月
茶碗と菓子器で味わう十二か月
於 東美アートフェア2025
絵刷毛目茶碗 / 象牙瓔珞文合子
絵刷毛目茶碗
高:5.8 径:12.8
象牙瓔珞文合子
高:5.6 径:5.5
企画展「日々好日 – Hibiyokihi」
茶碗と菓子器で味わう十二か月
茶碗と菓子器で味わう十二か月
於 東美アートフェア2025
斗々屋茶碗 石州箱 / 南鐐ヘギ目銘々皿
斗々屋茶碗 石州箱
高:5.4 径:15.0
南鐐ヘギ目銘々皿
企画展「日々好日 – Hibiyokihi」
茶碗と菓子器で味わう十二か月
茶碗と菓子器で味わう十二か月
於 東美アートフェア2025
のんかう黒茶碗 銘:簾 / 唐物独楽盆 本願寺伝来
のんかう黒茶碗 銘:簾 啐啄斎箱
高:7.4 径:12.5
唐物独楽盆 本願寺伝来
高:5.3 径:18.1
企画展「日々好日 – Hibiyokihi」
茶碗と菓子器で味わう十二か月
茶碗と菓子器で味わう十二か月
於 東美アートフェア2025
絵高麗梅鉢文茶碗 / 古染付蓮葉形小皿
絵高麗梅鉢文茶碗 〈東美アートフェア2025図録掲載作品〉
了々斎箱 紀州徳川家伝来Painted Goryeo-Style Tea Bowl
with Plum Blossom Design
高:4.9 径:15.9
古染付蓮葉形小皿 山水人物文
高:4.9 径:15.9
企画展「日々好日 – Hibiyokihi」
茶碗と菓子器で味わう十二か月
茶碗と菓子器で味わう十二か月
於 東美アートフェア2025